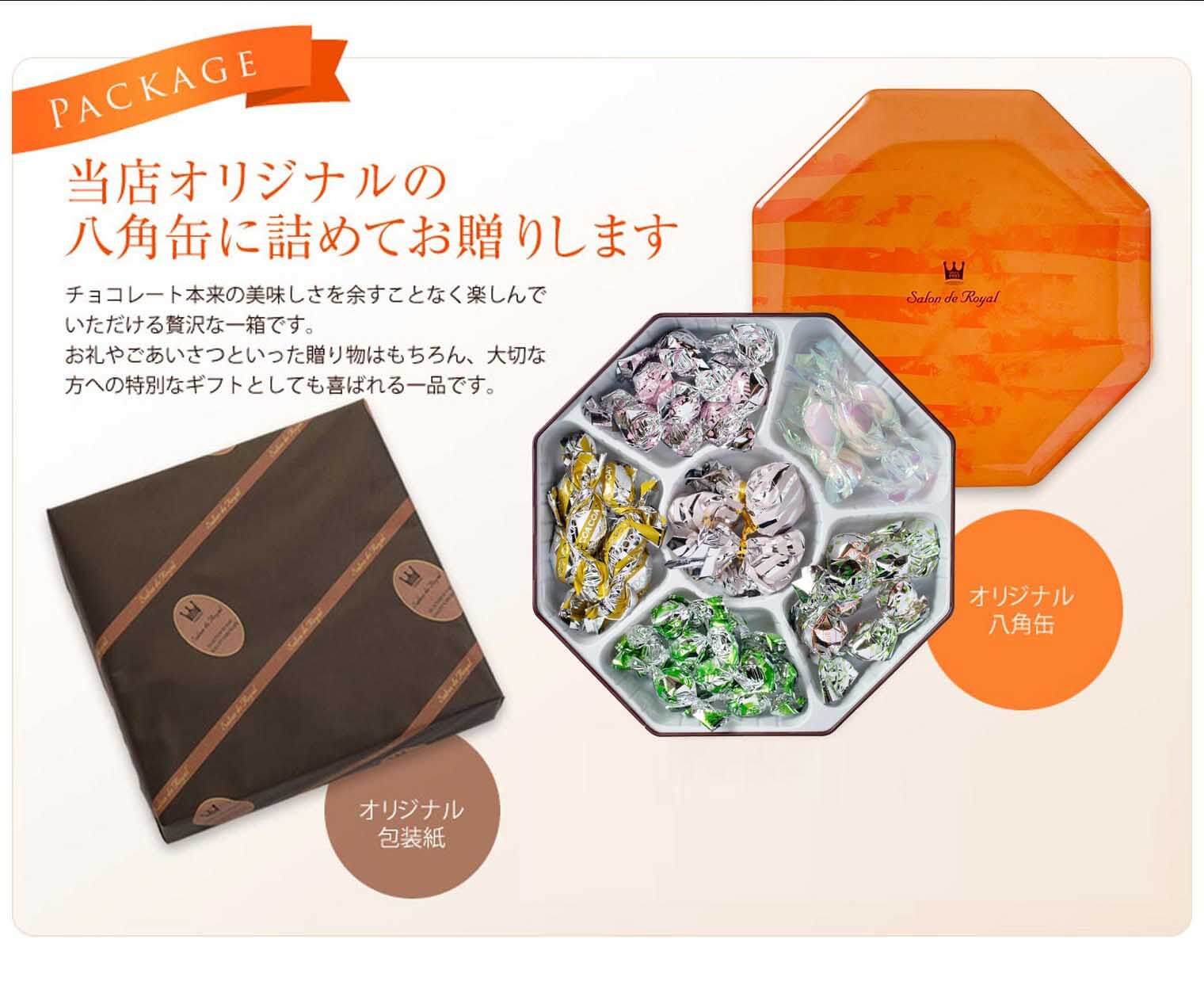2025.09.30
チョコレートの豆知識を紹介!面白い雑学や歴史を解説
「チョコレートの豆知識が知りたい」
「チョコレートの面白い歴史や雑学はある?」
チョコレートは古代では「神の飲み物」と呼ばれ、カカオ豆は通貨として使われていた歴史があります。
また、世界一チョコレートを消費する国はスイスで、年間一人当たり約9~12kgも食べているのです。
今回は、「あまり知られていないチョコレートの豆知識17選」について詳しく解説していきます。
普段何気なく食べているチョコレートの奥深い世界を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
あまり知られていないチョコレートの豆知識17選
チョコレートに関する驚きの豆知識は以下の通りです。
- ・チョコレートはもともと飲み物として楽しまれていた
- ・板状で食べられるようになったのは技術革新のおかげ
- ・カカオ豆は古代メソアメリカで通貨として使われていた
- ・老化防止に役立つポリフェノールが豊富に含まれている
- ・古代では薬としても使用されていた
- ・カカオ豆の生産量世界一はコートジボワール
- ・日本でチョコレートが一般に知られるようになったのは幕末
- ・「チョコを食べ過ぎると鼻血が出る」は科学的根拠がない
- ・「チョコレート」という名前の由来は実ははっきりしていない
- ・板チョコの溝は冷ましやすさ&割りやすさのために作られている
- ・熟したカカオの実は酸味が強い
- ・チョコレートは「神の飲み物」として扱われていた
- ・ベルギーは高級チョコレート文化とパッケージング発祥の地
- ・アルミ箔包装で品質を保護し香りを閉じ込めている
- ・カカオは熱帯でしか育たない植物
- ・世界で1番チョコレートを食べる国は「スイス」
- ・チョコレートの漢字表記は「当て字」でいくつか存在する
普段何気なく食べているチョコレートにも、こんなに多くの驚きの秘密が隠されているのです。
それでは上記の豆知識について詳しく解説していきます。
チョコレートはもともと飲み物として楽しまれていた
古代のマヤ文明やアステカ文明では、カカオ豆をすりつぶし、水や唐辛子、とうもろこしなどを混ぜて飲む“ショコラトル”という飲料が主流でした。
カカオそのものは大変貴重で、王族や特権階級の特別な飲み物だったのです。
現代のメキシコでは今でも朝にチョコレートドリンクを飲む習慣があるほどです。
また、日本にチョコレートが伝わった際も、砂糖と一緒にお湯に溶かして飲む薬のような使われ方をしていました。
チョコレートが板状で食べられるようになったのは技術革新のおかげ
チョコレートが板状で食べられるようになったのは技術革新のおかげです。
19世紀にカカオバターを抽出し、成形する革新的な技術が開発されたことにあります。
これによって、液体だったチョコレートを型に流して固める「板チョコレート」が作られるようになりました。
イギリス人ジョセフ・フライがココアバターを加えて冷やし固めたことで、口に入れると体温で溶ける固形チョコレートが誕生しました。
カカオ豆」は古代メソアメリカで通貨として使われていた
カカオ豆は古代メソアメリカで通貨として使われていました。
カカオ豆が当時とても貴重で保存が効き、持ち運びもしやすいことから、様々な品物やサービスとの交換に適していたためです。
実際にアステカやマヤの時代には、うさぎや七面鳥、さらには奴隷一人に至るまで、カカオ豆の粒数で価値が決められていました。
例えば、七面鳥の卵がカカオ豆3粒、奴隷1人が100粒といった具体的な相場が残っています。
こうしたカカオ豆の利用はスペイン人到来後も続き、労働者の報酬や罰金の支払いにも使われていました。
チョコレートには老化防止に役立つポリフェノールが豊富に含まれている
チョコレートには老化の予防に役立つ成分が含まれています。
主原料であるカカオに多く含まれる「カカオポリフェノール」が、体の中で活性酸素を除去してくれる強い抗酸化作用を持っているためです。
例えば、高カカオチョコレートに含まれるポリフェノール量は100gあたり2,540mgにもなり、他の食品よりも非常に多いのが特徴です。
体内で発生した活性酸素を素早く消去し、肌のダメージや加齢によるトラブルを予防する働きが期待できるのです。
古代では薬としても使用されていた
チョコレートは、実は古代で薬としても使われていたという意外な事実があります。
なぜなら、カカオは高い栄養価を持ち、「神の食べ物」と呼ばれていたうえ、あらゆる病気や不調の治療に使われた歴史があるからです。
例えば、古代メソアメリカのマヤやアステカ文明では、チョコレートは飲み物として親しまれ、薬草と混ぜて歯痛や喉の炎症、腹痛、解熱、毒消し、さらには催乳など、さまざまな症状に効く万能薬とされていました。
このため、今のようなお菓子というよりも、むしろ貴族や王族が健康維持のために飲む医薬品としての役割が強かったのです。
カカオ豆の生産量世界一はコートジボワール
カカオ豆の生産量が世界一なのはコートジボワールです。
カカオ栽培に適した気候や土地の条件、そして長年にわたり農業政策でカカオ開発を推進してきた歴史が背景にあります。
フランス植民地時代から大規模にカカオ生産が始まり、生産効率や量を重視し続けてきました。
2023年の国際連合食糧農業機関(FAO)の統計によると、コートジボワールは約237万トンのカカオ豆を生産しており、これは2位のガーナを大きく上回っています。
これは全世界の約4割を占める規模で、まさに圧倒的な生産量と言えます。
日本でチョコレートが一般に知られるようになったのは幕末
日本でチョコレートが一般に知られるようになったのは、実は幕末の時代です。
幕末にヨーロッパへ派遣された使節団が現地でチョコレート工場を見学し、日本にその存在が広く伝わったためです。
例えば、文久遣欧使節団がチョコレート工場を訪れたことや、フランス留学中の徳川昭武が日記に「ココアを喫んだ」と記していることが具体的な例として挙げられます。
このように、幕末の国際交流によってチョコレートは日本で幅広く知られるようになりました。
「チョコを食べ過ぎると鼻血が出る」は科学的根拠がない
「チョコを食べ過ぎると鼻血が出る」という説には、科学的な根拠はありません。
鼻血は主に鼻の粘膜や毛細血管が傷ついたり、刺激を受けたりすることで発生するものです。
チョコレート自体に鼻血を直接引き起こす成分は含まれていません。
確かに、チョコレートには血流を一時的に促進するポリフェノールやテオブロミンなどの成分がありますが、これが鼻血の原因になるという医学的根拠は示されていません。
「チョコレート」という名前の由来は実ははっきりしていない
「チョコレート」という言葉の語源は明確に分かっていません。
たとえば、アステカ民族のナワトル語で「苦い水」を意味する「チョコラトル」や、スペイン語・マヤ語との関連を指摘する説などがあります。
しかし実際には「チョコラトル」という単語が存在しないとの指摘もあり、どれが正しいかは分かっていません。
現地語由来の「ショコラトル」説が最も有名ですが、専門家の調査でその単語が使われていた確証は未だ見つかっていません。
「苦い水」や「酸味のある飲み物」といった意味付けも、後世の解釈の可能性があるのです。
板チョコの溝は冷ましやすさ&割りやすさのために作られている
チョコの溝は、冷ましやすさと割りやすさのために作られています。
溝をつけることで板チョコの表面積が増え、熱が効率良く伝わりやすくなり、短時間で均一に冷やして固めることが可能になります。
また、冷却時に生じる収縮の影響で型から取り外しやすくなりますし、食べる際も自然に割りやすい形状となるため、消費者も便利に感じるのです。
熟したカカオの実は酸味が強い
熟したカカオの実は酸味が強いです。
カカオの果肉と豆に含まれる自然な有機酸が多いためです。特に収穫後に行われる発酵の過程で酢酸や乳酸などの酸味成分が生成され、これがカカオの酸っぱさに繋がります。また、カカオが熱帯フルーツであることから、果肉自体もライチやマンゴスチンのように爽やかな酸味を持っています。
例えば、実際に熟したカカオの果肉を食べるとフルーティーで強い酸味が感じられます。
また、発酵が上手く進むとカカオ豆の酸味が強まり、これが高カカオのチョコレートの味わいにも反映されます。
逆に、発酵が不十分だと酸味が少なく、逆に渋みや雑味が残ります。
チョコレートは「神の飲み物」として扱われていた
メソアメリカのマヤ文明やアステカ文明では、チョコレートの原料であるカカオ豆を使用した飲み物が、特別な儀式や王族の間で愛飲されていました。
また、カカオ豆そのものも貨幣のような価値を持っており、特権階級だけが味わえる特別な存在でした。
例えば、アステカの皇帝は黄金のカップで1日に50杯ものカカオ飲料を飲んだという逸話も残っており、力や活力の源として重宝されていました。
カカオ飲料は、甘くもなく、香辛料や花の香りをつけて作られていたそうです。
ベルギーは高級チョコレート文化とパッケージング発祥の地
ベルギーは高級チョコレート文化とパッケージング発祥の地です。
ベルギーでは古くからカカオの流通や製造技術が発展し、王室御用達ブランドが誕生したことが挙げられます。
ベルギーのノイハウスが1912年に世界初のボンボンショコラを発明し、1915年にはチョコレート専用のパッケージ「バロタン」を開発しました。これは、贈答品としての高級チョコレート文化の礎です。
つまり、ベルギーは高級チョコレートと美しいパッケージの本場であり、世界中の愛好家から高く評価されているのです。
チョコレートはアルミ箔包装で品質を保護し香りを閉じ込めている
チョコレートはアルミ箔包装によって品質を守り、香りも逃さず閉じ込めています。
普通の紙包装だと香りが抜け、他のにおいが移ってしまう心配がありますが、アルミ箔はきめ細かい金属素材なので気体や香りが通りません。
実際、国内外の多くの有名メーカーや高級チョコレートは、鮮度と風味を長く保つためにアルミ箔で個包装をしています。
また、家庭で開封後のチョコレートを保存する際も、香りや品質の低下を防ぐためにアルミホイルで包む方法が推奨されています。
カカオは熱帯でしか育たない植物
カカオは熱帯でしか育たない植物です。
カカオの木が成長し実をつけるためには、1年を通じて平均気温が27℃以上、高温多湿、さらに気温の変動が少ないなど、非常に限られた気候条件が必要だからです。
カカオ生産地は、赤道を挟んで南北緯20度以内の狭いエリアにある西アフリカ、中南米、東南アジアなどです。
高温多湿の環境と毎年安定した降雨、しかも日照時間も十分でなければ、カカオの木はうまく育ちません。
日本など温帯の地域では、これらの条件を満たすことが難しいため、基本的にカカオは育てられません。
世界で1番チョコレートを食べる国は「スイス」
世界で1番チョコレートを食べる国は「スイス」です。
国民一人当たりの年間消費量は約9~12kgとされており、日本人の数倍以上にもなります。
その背景には、スイスが1870年代に世界で初めてミルクチョコレートを開発したこと、国内で質の高いブランド(リンツ、ネスレなど)が多く存在すること、また日常的に家族や仲間とチョコレートを楽しむ習慣が深く根付いている点が挙げられます。
食事やおやつの際にも気軽にチョコレートを楽しむ習慣が一般的です。
さらに、観光客にも質の高いスイスチョコは人気で、土産としても選ばれることが多いです。
チョコレートの漢字表記は「当て字」でいくつか存在する
チョコレートの漢字表記は「貯古齢糖」「猪口令糖」「千代古齢糖」「知古辣」「楂古聿」「猪口冷糖」「知古辣他」「貯古令糖」「貯古冷糖」「猪口齢糖」「血汚齢糖」「千代古令糖」など、実は12種類ほどもあります。
明治時代に西洋菓子のチョコレートが日本に入ってきた際、カタカナ表記がまだ普及しておらず、音に近い漢字を強引に当てはめて表現していたためです。
商品広告や文学作品などで様々な表記が使われました。
当時はチョコレートが高価な洋菓子で身近でなかったこともあり、「血汚齢糖」など、誤解や噂が元になった字もあります。
まとめ
チョコレートには飲み物としての歴史や通貨としての役割、老化防止に役立つポリフェノール、薬としての利用など、豆知識が数多く存在します。
普段何気なく食べているチョコレートには、文化・歴史・健康の側面で非常に深い背景が隠されているのです。
今回紹介した知識をきっかけに、チョコレートをただのお菓子として楽しむだけでなく、その歴史や奥深さに触れてみてください。